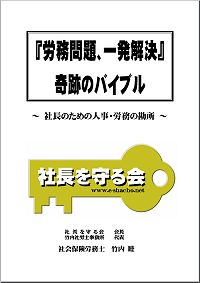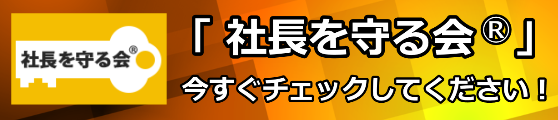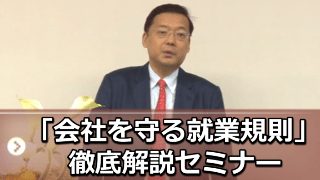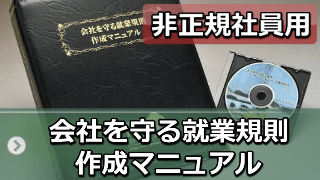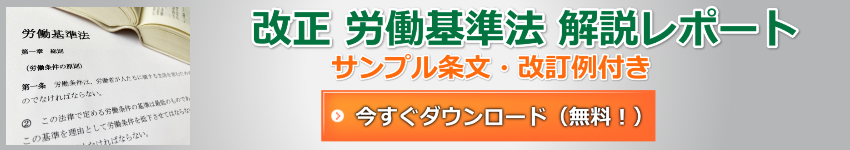年次有給休暇の按分付与は可能?
- 年度途中の退職者について、退職日までの期間に応じて、按分した日数を付与することはできるのでしょうか?
- 年度途中の退職者であっても、過去の出勤率の要件さえ満たせば、法定の日数は付与せざるを得ません。
- 労基法上の年次有給休暇の発生要件
- 事例詳細
労基法上の年次有給休暇の発生要件
- 年次有給休暇の発生要件は、直近1年(初年度は6ヶ月)の出勤率が80%以上であることが規定されているのみ
事例詳細
当社の事業年度は7月1日から翌年6月30日で、年次有給休暇についても、入社初年度を除き、毎年7月1日に一斉に付与しています。
ところで、当社には、入社して7年になるAという営業社員がいます。
当初から可もなく不可もなくという感じで、これまで雇用してきましたが、最近は特に営業成績が振るわず、上司が指導しても、反抗的な態度を取るようになったりして、社内で問題になっていました。
正直なところ、早く辞めてほしいと思っていましたが、顧問社労士からは、「この状態で解雇したとしても、争いになった場合には、解雇は無効と判断される可能性が高い」とのアドバイスを受けていたので、A社員の問題行動があれば注意し、それを記録することで、来るべき時に備えていたところです。
そんな折、当社の事業年度末も差し迫った6月20日の夕方に、A社員から上司である営業部長に話があるとのことで、応接室で面談することになりました。
やぁAさん、調子はどうですか。ところで、話しがあるって、急にどうしたんだい?
あのー、営業部長、実は、一身上の都合で、退職させていただきたいと思います。
なにーっ! そうかあ。それは残念だなあ。それで、退職希望日はいつなんだ?
こちらが退職届になりますが、8月28日をもって、退職とさせていただきたいと思います。
退職することついては、分かった。しかし、8月28日って、2ヶ月も先じゃないか。引き継ぎにも、それほど時間がかからないだろうから、もう少し前倒しでも構わないけどな。
引き継ぎについては、3日もあれば十分だと思いますので、6月26日以降は有給休暇を取得したいと思います。
有給休暇を取得するとしても、8月28日まで休むほどは、残っていないだろう。
現在の残日数は21日あります。21日のうち今月末に時効で消滅する5日については6月26日から取得します。残りの16日は次年度に繰り越され、7月1日には新たに18日発生しますので、34日の有給休暇が残ります。これを全て取得すると8月28日になります。
なんだって!? 確かに7月1日は有給休暇の付与日だけど、向こう1年間の勤務に対して18日発生するんであって、少なくとも8月28日に退職するのが確定しているんだから、18日ではなくて、7月と8月分、12ヶ月分の2で、3日なんじゃないか?
年度途中の退職者への付与日数は?
年次有給休暇の付与日を統一している会社は多く、この場合、年度途中の採用者に関しては、採用日から年次有給休暇の付与日までの期間に応じて、按分した日数を付与していることもあります。
年次有給休暇は勤続6ヶ月経過日に10日付与されていればよく、それ以前に按分した日数を付与することは問題ありません。
一方で、年度途中の退職者について、退職日までの期間に応じて、按分した日数を付与することはできるのでしょうか。
これに関し裁判例では、以下の通り、退職者に対する按分付与を否定しています。
年次有給休暇には、労働者の過去の勤務に対する一種の報償という面もあることは否定できないから、中途退職者を、年次有給休暇について、中途採用者より優遇しても、公平に反するとまでいうことはできない。(中略)中途退職者に対し、在籍期間に比例按分した日数を年次有給休暇として与えるとすれば、中途退職者の中で労働基準法第39条の定める日数に満たない者も出てくる。そうすると、これらの者に関しては、年次有給休暇の最低日数を定める右条文に違反することになろう。
法文上も、年次有給休暇の発生要件は、直近1年(初年度は6ヶ月)の出勤率が80%以上であることが規定されているのみで、将来の継続勤務については、要件になっていません。
よって、年度途中の退職者であっても、過去の出勤率の要件さえ満たせば、法定の日数は付与せざるを得ません。
ただし、法定を上回る日数であれば、就業規則等にその旨を規定して、按分付与することは可能です。
年次有給休暇について正しく定めておかないと、不要なトラブルに発展する可能性があります。
就業規則への具体的な記載方法は、以下のセミナーで詳細を解説しています。
セミナー参加者特典として、無料個別相談で疑問点をすべて解消することもできます。
「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー
竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2025年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。
オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法
社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。
社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。
当サイトで初めてご購入される方、会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。
会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。