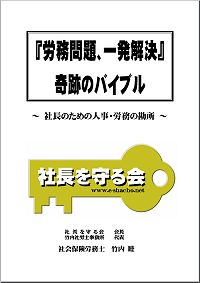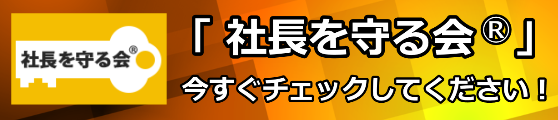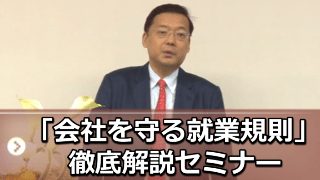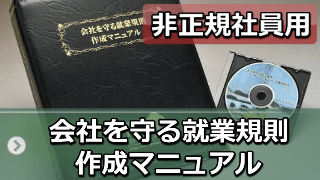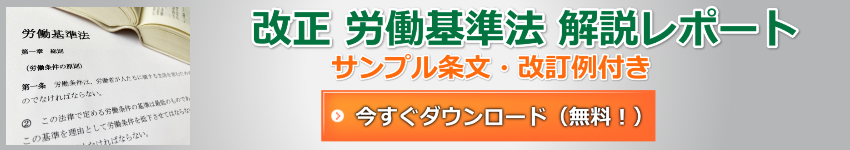妊娠出産時の不利益取り扱いで揉めたら?
- 社員の妊娠・出産に対し、会社はどのように対応するべきなのでしょうか?
- 男女雇用機会均等法により、妊娠・出産等を理由とする解雇その他の不利益な取り扱いは禁止されています。育児休業や育児短時間勤務について就業規則に規定し、社員に周知しておきましょう。
- 男女雇用機会均等法の原則
- 実務上の留意点
- 事例詳細
男女雇用機会均等法の原則
- 妊娠・出産等を理由とする解雇その他の不利益な取り扱いは禁止されている
- ただし、本人の企業秩序違反や勤怠不良等、他の要因によって解雇等を行うことは、同法令の問題にはならない
実務上の留意点
- 妊娠・出産する社員の処分を検討する際は、それ以外の理由により解雇等をしたことを具体的に主張・立証することができなければ、妊娠・出産等を理由に解雇等をしたと判断される可能性が高いため、注意が必要
- 現代、妊娠・出産・育児にまつわる母性保護に関しては、最も重要な国家施策の一つとして捉えられている
事例詳細
当社は東京郊外に本社を構える、従業員規模約20人の不動産販売会社です。当社には、総務・経理・庶務等を兼ねた事務職が3名いますが、この度1名が退職することになりました。
この社員は、入社5年目になる30歳の女性社員で、いわゆる結婚退職です。この社員の退職に伴い、当社はすぐに求人募集を行ったところ、幸いにも他社で総務・経理経験のある33歳の既婚女性(A社員)を採用することができました。
経験者ということに加え、既婚で子育ても一段落し、当分出産の予定もないということも採用を決めた理由の一つです。ところが、入社6ヶ月が経過したころ、総務課長はA社員から、唐突に相談を持ちかけられました。
あのー総務課長、実は相談があるのですが・・・。実は私、妊娠しているようで…。
えーっ! そっ、そっ、そうなんですかー! ・・・で、今は妊娠何ヶ月くらいなんですか?
実は今、妊娠3ヶ月目なんです・・・。一応、母子ともに健康ということではありますが。
3ヶ月目ですかあ。ということは、今が4月ですから、予定日は年末頃になりますかね。
そうですね。それでお願いなんですけど、まだ先の話になりますが、産休と育休を取得したいと考えていますので、その際はよろしくお願いしたいと思いまして。
あっ、そ、そ、そうですね~。事情は分かりました。そのように社長にも伝えておきますよ。
すみませんが総務課長、ご迷惑をお掛けしますが、その節はどうかよろしくお願いします。
総務課長は、いきなりの相談に戸惑いながらも、急ぎ社長に相談することにしました。
しゃ、しゃ、社長! 実は、あのA社員から、妊娠したっていう報告があったんですよ。
ひぇーーー何だってぇーーーっ! ・・・それで、よ、よ、予定日は一体いつなんだ?
予定日は、年末頃だということで、時期が近づいてきたら、産休と育休を取得したいのでお願いしますとのことでした。
うぅ~ん。確か面接のときは、子育ても一段落ついて仕事に専念したいから、出産の予定は当分ないって、いってたよなぁ。どうする?
そうですねぇ。産前産後の休業や育児休業は、法律上の義務ですから、仕方ないですかね?
・・・そうはいってもなぁ・・・。育児休業まで取得するとすれば、いつまで休むことになるんだね。
育児休業は、最長で子が2歳になるまでですから、来年の冬頃まででしょうか。
そうかぁ。それは厳しいなぁ・・・。総務課長、申し訳ないんだが、何とかA社員を説得して、退職してもらうようにしてもらえないだろうか?
わ、わ、分かりました。・・・難しいとは思いますが、何とかやるだけやってみます。
こうして数日後、総務課長は、A社員を呼んで話をすることになりました。
最近体調の方はどうですか? 母体や胎児の健康が第一ですから、無理しないでくださいね。
えぇ、体調が優れない時もあったりして、皆さんにはご迷惑をお掛けしていることもあるかも知れません。でも大丈夫です。
・・・しかし、今後Aさんが長期で休業に入ると、誰か別の人を採用することも検討しなければならないし、やはりAさんが母子ともに健康で、元気な子を産んでもらうのが、お互いに一番いいんじゃないかと思うんだが・・・。
・・・総務課長! それって、私に退職しろと暗におっしゃっているんじゃないんですか?
いやいや、そんなつもりではないんですが、出産して元気になったら、またうちで働いたらどうかなって・・・。
それって、いったん退職して、出産したら、その時にまた応募してこいってことなんですか?
んー・・・。まぁ簡単にいえば、そ、そ、そういうことになりますが、・・・いかがですか?
会社の気持ちも理解できないわけではありませんが、私は産休を取得したいと思っています。もし、どうしても会社が認めてくれないなら、労働局に相談しに行ってきます。
妊娠・出産等を理由とする解雇その他の不利益な取り扱いは禁止されている
男女雇用機会均等法により、妊娠・出産等を理由とする解雇その他の不利益な取り扱いは禁止されており(育児休業等を取得しようとしたこと等を理由とする不利益取り扱いについても、育児介護休業法により禁止されています)、こうした妊娠・出産等に起因する紛争については裁判だけでなく、都道府県労働局長による助言・指導・勧告、あるいは紛争調整委員会による調停の対象にもなっています。

なお、ここでいう「理由とする」とは、妊娠・出産等と解雇その他不利益な取り扱いとの間に因果関係があることをいいます。
よって、妊娠・出産等以外の理由、例えば本人の企業秩序違反や勤怠不良等、他の要因によって解雇等を行うことは、同法令の問題にはなりません。
ただし、後に裁判になった場合、妊娠・出産等ではない理由により解雇等をしたことを具体的に主張・立証することができなければ、妊娠・出産等を理由に解雇等をしたと判断される可能性が高いといえますので、注意が必要です。
また、「解雇その他不利益な取り扱い」には、退職を強要することも含まれますので、退職勧奨の結果、退職について労働者より同意を得たとしても、それが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、退職を強要したとして、「解雇その他不利益な取り扱い」にあたる場合も考えられます。
さて、少子高齢化が加速度的に進行している現代社会においては、現在そして今後においても、女性を活用することなしに、日本の雇用社会を維持し、国際競争力を維持する道はないといっても過言ではありません。
そのため国も、妊娠・出産・育児にまつわる母性保護に関しては、最も重要な国家施策の一つとして捉えています。
今も昔もこの問題は、会社にとっては頭の痛い問題ではありますが、少なくとも昭和の時代とは異なり、時代が変化したことを認識しておく必要があるでしょう。
法律上、育児休業や育児短時間勤務は誰でも利用できる制度であることを、就業規則などで社員に周知しておくことが、今後のトラブルを防ぐには必須だといえます。
育児休業や育児短時間勤務ついて正しく定めておかないと、不要なトラブルに発展する可能性があります。
就業規則への具体的な記載方法は、以下のセミナーで詳細を解説しています。
セミナー参加者特典として、無料個別相談で疑問点をすべて解消することもできます。
「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー
竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2025年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。
オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法
社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。
社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。
当サイトで初めてご購入される方、会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。
会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。