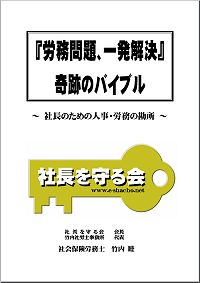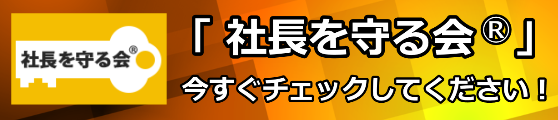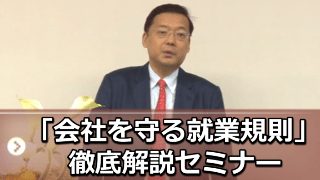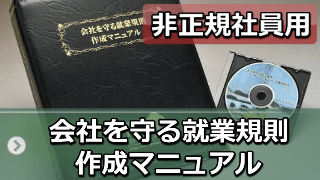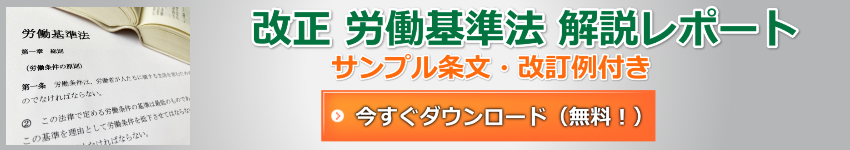過払い賃金の控除は認められるか?
- ミスにより賃金を多く支払ってしまった場合、賃金から控除することはできるのでしょうか?
- 書面により、過払い賃金の清算も含めた賃金控除に関する協定を締結しておけば、スムーズに処理ができるでしょう。
- 労使協定による賃金控除
- 調整的相殺
- 事例詳細
労使協定による賃金控除
- 多くの場合、「支給日に在籍していることが賞与の支給要件の一つである」と就業規則に定めてあれば、その規定は有効
- ただし、会社と労働組合の交渉の結果、賞与の支給日が遅れた場合に、支給日を変更したときには変更日における在籍要件を満たす必要があるといった慣行がないのであれば、給与規程で定められていた支給日以前に在籍していた者には、賞与の支払い義務がある
調整的相殺
- 過払い賃金を精算する調整的相殺は、「1.過払いのあった時期と賃金の清算時期とが合理的に密接した時期になされる」、「2.あらかじめ労働者に予告しておく」、「3.その額が、多額にわたらず、労働者の経済生活を脅かさない」場合、労使協定がなくても認められる
- 民法第510条、および民事執行法第152条により、控除限度額は賃金額の4分の1となる
事例詳細
当社は、従業員規模が30名ほどの建設会社です。
Aさんは経理を担当しており、先月誤ってBさんの給与を余分に支払ってしまいました。
社長にその件を相談したところ、Aさんから直にBさんに事情を伝えることになりました。
Bさん、すみません。私の計算ミスで、先月支払った給与(30万)のうち、1万円多く支払っていることがわかりました。
え? そうなの? 給与明細は詳しくみてなかったので、分からなかったな。
それで、来月支給の給与からその額を差し引いて支払ってもよろしいでしょうか?
え? でもそっちのミスなんだし、いまさら言われても、返す必要あるの?
確かに私に原因がありましたが、誤って支払った分を返すのは当然ではないしょうか?
Aさんのミスにより、余分に支払ってしまった給与を、次回のBさんの給与から控除するのは、法律上問題ないのでしょうか。
賃金は全額払いが原則
賃金は原則として全額支払わなければなりません。ただし、労使協定で定めた費用について賃金から控除することができる旨が、就業規則等で定められており、実際に労使協定を締結している場合は、例外として控除が認められます。
労使協定を締結していない場合は、認められるかどうかという議論になりますが、その場合は原則的に、先月の過払い分の1万円を使用者が、Bさんに対して有する不当利得返還請求権で、その返済を求めることになります。
Bさんが、それにまったく応じないというのであれば、訴訟に発展するということになります。
しかし、長期的な労働契約の中では今回のようなケースだけでなく、欠勤控除等の計算の締切日の関係から、少額の賃金の過払いになることも想定され、それも同じように、原則的な取り扱いをしていては、とても煩雑になってしまいます。
一定の賃金の調整的な相殺を認めることは労働者にとっても必ずしも不利になるとはいえません。
過払い賃金の清算が認められる場合とは?
そこで過払い賃金の清算のための調整的相殺(ある賃金計算期間に生じた賃金の過払いを後の期間の賃金から控除すること)に関し、最高裁では、以下3つを要件に、労使協定がなくても控除を認めています。
- 過払いのあった時期と賃金の清算時期とが合理的に密接した時期になされること
- あらかじめ労働者に予告しておくこと
- その額が、多額にわたらず、労働者の経済生活を脅かさないこと
行政上も、払い過ぎた分を翌月に差し引いて清算する程度は認めても、労働者の生活を害する恐れはないと考えられることから、賃金計算上の取り扱いとして、労使協定がなくても、労働基準法違反としては取り扱わないという立場がとられています。(昭和23.9.14 基発第1357号)
なお、過払賃金の清算調整のための賃金控除額は、法律上の使用者の一方的意思表示としての相殺ですから、民法第510条、民事執行法第152条の適用を受け、最大限4分の1までしか控除できないことに留意する必要があります。
以上の事から、過払い分については、賃金控除の労使協定を締結している場合は、控除することができ、労使協定を締結していない場合であっても、上記の 1~3に該当するかどうかで判断がなされるということになります。
労使協定の締結でスムーズな処理を!
今回のケースでは、問題が発生した時期と清算時期が近いということ、事前に労働者に予告しているということ、控除額も給与の1割以下であるということから、例外として認められる可能性が高いと考えられます。
しかし、こういった問題が生じた際にスムーズに処理ができるよう、過半数組合もしくは従業員の過半数代表者との間で、書面により賃金控除に関する協定(過払い賃金の清算も含め)を締結しておき、法令上の問題をクリアさせておくことが労務管理上適切だと考えます。
控除する賃金や控除の方法を正しく定めておかないと、不要なトラブルに発展する可能性があります。
就業規則への具体的な記載方法は、以下のセミナーで詳細を解説しています
セミナー参加者特典として、無料個別相談で疑問点をすべて解消することもできます。
「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー
竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2025年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。
オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法
社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。
社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。
当サイトで初めてご購入される方、会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。
会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。