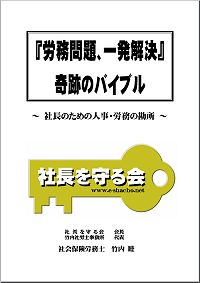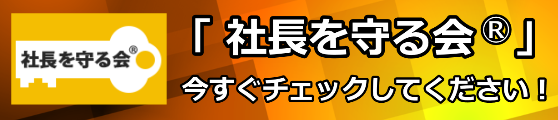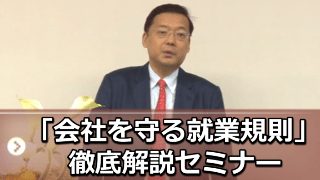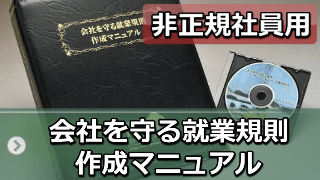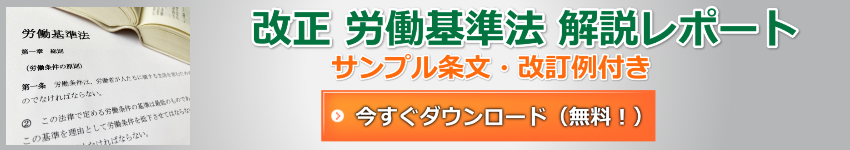賃金の一部前払いと賃金控除
- 賃金の一部を前払いしている会社が、社員に追加で前払い賃金を貸した場合、どのように賃金から控除すればよいのでしょうか?
- 事前に従業員に控除額について確認し、従業員と真の合意の上で控除することが必要です。
- 控除限度額と控除の方法
- 実務上の留意点
- 事例詳細
控除限度額と控除の方法
- 通勤手当、および公租公課を除外した賃金の4分の1が控除限度額となる
- 賃金前払いの分は、限度額とは別に控除できる
- 貸付金返済については、労使協定および従業員との個別合意がなければ賃金から控除できない
実務上の留意点
- 事前に従業員に控除額について確認し、従業員と真の合意の上で控除することが必要
事例詳細
個人タクシー事業を営む○×株式会社では、給与の締め日を末日とし、支払日は翌月5日としています。
それに加え、給与締め切り期間内の当月20日に、既往の労働に対する賃金の一部を前払いする「20日給与」と呼んでいる会社独自の制度があります。
ある月の21日です。
あの~社長、今月はいろいろと急な入用がありまして、20日給与で6万円前払いをしてもらいましたが、生活費が足りなくて・・・
そうか、それは大変だな~。急な入用なんていうのは結構続いたりするからね。
厚かましいお願いですが、もしよろしければ10万円ほど貸していただけませんか。
よし、わかった。いつも頑張ってくれているし、10万円貸そう。その分は給与から天引きして返済するということでいいかな。
はい。ありがとうございます。よかった~!!! とっても助かります~♪♪♪
経理部長、Aさんに10万円貸してあげたから来月の給与から天引きしておいてくれ。
分かりました。うちの会社の『賃金控除に関する労使協定』で賃金から控除できるとしている項目は、雇用保険や社会保険、源泉などの法定のもの以外に、社宅費、20日給与、貸付金が控除できるとなっていますので、貸付金の項目で10万円を天引きしておきますね。
そして、5日の給与支給日に、月給25万円(うち通勤手当1万円を含む)のAさんは、雇用保険、社会保険、および源泉などの公租公課として4万円、20日給与で支給された6万円、貸付金の10万円の合計20万円が給与から控除され、実際の支給額として5万円を受け取りました。
社長、今月の給与はたった5万円だけですか。これではとても生活なんてできません!
それは仕方ないだろ。貸した10万円を今回の給与から引いたから、その金額になるよ。
今月の給与から全額天引きされるとは思いませんでした。労基法では、賃金全額払いが原則って聞いたことがあります。これって労基法違反なんじゃないんですか!?
賃金の1/4を超える控除は違法となる!?
賃金控除について争われた不二タクシー事件(東京地裁 平21.11.16判決)では、以下のように示されました。
労基法24条1項ただし書きは、賃金の一部の控除を許容するものであるし、労働者の経済生活を脅かすことがないようにするという立法趣旨からすれば、労使協定を根拠に行う使用者の従業員の賃金からの控除については、民事執行法152条および民法510条に照らし、控除限度額は賃金額の4分の1にとどまる。
不二タクシー事件 東京地裁 平21.11.16判決
また、控除限度額を算定する前提となる賃金は、通勤手当、および公租公課を除外した額とするのが相当と判断されています。
さらに、「20日給与」については、賃金前払いそのものであることから、これを控除することは労使協定によるまでもなく、賃金全額払いの原則に反しないが、貸付金返済については、労使協定および従業員との個別合意がなければ賃金から控除できないとされました。
以上のことから裁判例に照らし合わせると、今回の場合は、25万円の給与から公租公課の4万円と通勤手当の1万円を引いた20万円が控除限度額を算定する賃金となり、控除できる金額はこれの4分の1ですので5万円ということになります。
もっとも、20日給与で賃金前払いをした6万円については控除できる金額とは別に考えますので、貸付金として天引きした10万円のうち、賃金の4分の1を超える5万円が労基法24条1項の賃金全額払いに反し違法ということになります。
ただし、「労働者の自由な意思」に基づく賃金控除については全額払いの原則に抵触しません。
よって、賃金の4分の1を超えるような金額を控除することが発生するような場合は、労使協定に控除項目があるからといって自動的に控除するのではなく、事前に従業員に控除額について確認し、従業員と真の合意の上で控除することが必要です。
なお、就業規則には、賃金から控除できるものとして、「法令で定めるもの(源泉所得税や住民税など)、および従業員の過半数を代表する者との協定により定めたもの」などと明記しておくとよいでしょう。
賃金について正しく定めておかないと、不要なトラブルに発展する可能性があります。
就業規則への具体的な記載方法は、以下のセミナーで詳細を解説しています。
セミナー参加者特典として、無料個別相談で疑問点をすべて解消することもできます。
「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー
竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2025年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。
オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法
社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。
社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。
当サイトで初めてご購入される方、会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。
会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。