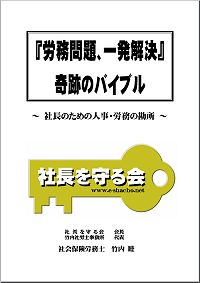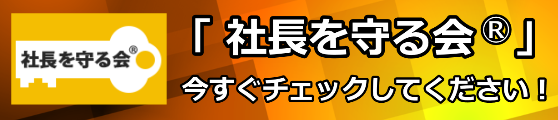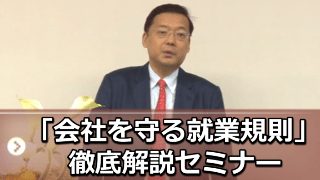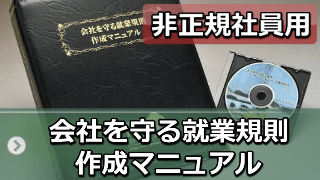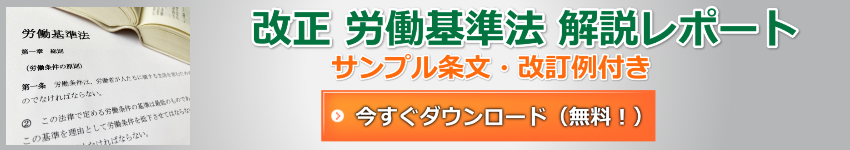休業手当支払義務のポイントは?
- 会社の引っ越し準備で社員が働けなかった場合にも、給与を支払わなければならないのでしょうか?
- 一部休業の場合、現実に勤務した時間に対して支払われた賃金が、平均賃金の100分の60以上であれば、労基法上は問題ありません。
- 民法と労基法の規定
- 休業手当の金額
- 事例詳細
民法と労基法の規定
- 債権者(会社)の責めに帰すべき事由によって債務(労務)を履行(提供)することができなくなったときは、債務者(労働者)は反対給付(賃金)を受ける権利を失わない。(民法第536条2項)
- 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。(労働基準法第26条)
休業手当の金額
- 一部休業の場合、現実に勤務した時間に対して支払われた賃金が、平均賃金の100分の60に満たない場合についてのみ、その差額を支払えば労基法第26条違反は問われない
事例詳細
当社は、この度本社を移転することにしました。引っ越しは、土日の休日のうち土曜日に行いますが、前日の金曜日は対外的には休業として、引っ越しの準備をすることになっています。
皆さん、お疲れ様です。これから引っ越しの準備をしてもらいますが、明日もありますので、早めに終わらせましょう。
こうして、皆で黙々と作業を行った結果、午前中には準備が終了しましたが、パソコン等も整理してしまったので、午後は仕事になりませんから、皆さんには帰宅してもらうことにしました。
あのさーーー。少し気になったんだけどさーーー、午後の給料って、引かれるのかな?
うちはノーワーク・ノーペイだから、働いた時間分しか払われないんじゃない?
えっ、そうなの!?でもさーーー、午後働けなかったのは、会社のせいなんじゃない?
そうだよね・・・、会社のせいだよね。それだったら、休業手当が出るのかなぁ?
休業手当を支払う義務は生じる?
さて、労基法第26条は、使用者の責めに帰すべき事由により休業させる場合には、平均賃金の100分の60以上の額の休業手当の支払いを義務付けています。
一方、民法第536条2項では、以下のように規定されています。
第536条2項
債権者(会社)の責めに帰すべき事由によって債務(労務)を履行(提供)することができなくなったときは、債務者(労働者)は反対給付(賃金)を受ける権利を失わない。
通常の賃金との差額について、会社から支給を受ける権利は有していることになります。
とはいえ、この民法の規定は、会社と労働者の特約によって、効力を失わせることが可能ですので、最低基準を定めた労基法では、罰則付きで、平均賃金の100分の60の休業手当を支払う義務を、使用者に負わせているということになります。
そこで、先ほどの例を考えてみると、金曜日の午前中は勤務したものの、午後は会社から帰宅するように指示があったために休業になりましたから、この一部休業の部分を含め、休業手当について、どのように考えるのかが問題となります。
この場合、午後の一部休業についても、休業手当を支払う必要があるのでしょうか。
1日の休業につき平均賃金の60%を支払っているかどうか

この点につき、行政通達では、現実に勤務した時間に対して支払われた賃金が、平均賃金の100分の60に満たない場合についてのみ、その差額を支払えば同法第26条違反には問わない(昭27.8.7 基収第3445号)とされています。
つまり、金曜の午前中の勤務に対して支払われた賃金が、平均賃金の60%を超えているときには、この日の午後が休業になったとしても、別途休業手当を支払う義務は、労基法上生じないということです。
具体的には、仮にAさんの平均賃金が8,000円、時間単価が1,000円だとします。
金曜日の勤務は午前中の3時間で、午後の5時間は休業したとすれば、現実に勤務した時間に対して支払われる賃金は、3,000円ということになります。
Aさんの平均賃金の60%は4,800円ですので、この場合は、不足の1,800円を支給する必要があるということになります。
午後の休業した5時間分に相当する賃金である5,000円の60%である3,000円を午後の休業手当として支払い、また現実に勤務した午前の3時間分に相当する3,000円と合算して、6,000円を支払う義務は生じません。
要するに、一部休業があったとしても、結果として、平均賃金の60%の休業手当が支払われていれば、労基法上は適法ということになります。
しかし、これですと、使用者の責めに帰すべき事由による休業という債務不履行責任が、実労働時間に対する賃金の支払いをもって、埋没してしまうという結果を招くことになりますが、既述のとおり、民法上では、労働者は100%の賃金請求権を持っているということになります。
なお、就業規則には、「会社の責めに帰すべき事由により社員を休業させる場合は、民法536条2項の定めにかかわらず、休業1日につき平均賃金の100分の60を支給する。」などと規定し、民法第536条2項の適用を排除するよう明記しておくとよいと思います。
休業手当を含む賃金について正しく定めておかないと、不要なトラブルに発展する可能性があります。
就業規則への具体的な記載方法は、以下のセミナーで詳細を解説しています。
セミナー参加者特典として、無料個別相談で疑問点をすべて解消することもできます。
「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー
竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2026年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。
オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法
社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。
社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。
当サイトで初めてご購入される方、会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。
会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。