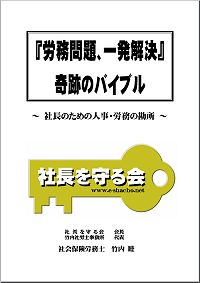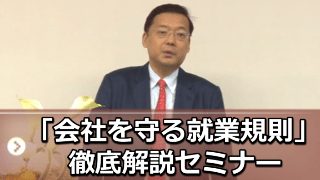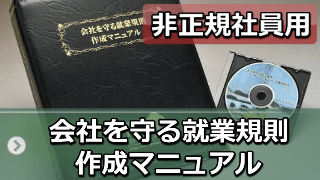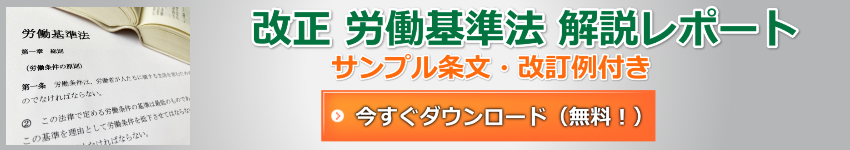年休の計画的付与の方法
- 年次有給休暇の計画的付与には、どのような方法がありますか?
- (1)事業場全体、(2)課や班ごと、(3)個人ごとに付与する3つの方法があります。
(1)事業場全体の一斉付与方式
事業場全体で、お盆や年末年始を休日にしているような場合、それらを休日に設定するのではなく、その日に年次有給休暇を一斉に取得させることが考えられます。
この場合、事業場全体に年次有給休暇を取得させるわけですから、年次有給休暇の残日数が5日以下の者の取り扱いが問題になります。
対象となる年次有給休暇日数のない(残日数が5日以下の)者には、特別の休暇を与えるか、少なくとも平均賃金の6割に相当する休業手当(労働基準法第26条)を支払う必要があることに留意してください。
(2)課、班別の単位による交替制方式
事業場全体で年次有給休暇を取得させることができない場合には、労働者を1班と2班に分け、1班は8月10日から12日まで、2班は8月16日から18日までというように、計画年休を振り分け、事業場は休業しないで乗り切るという方法も考えられます。
事業場は休業にならないので、休業手当の支払いが必要な者は発生しません。
(3)計画表による個人別の付与方式
上記(1)、(2)のいずれも採用しにくい場合は、個人ごとに年次有給休暇取得日を指定し、その指定された日に計画年休を取得するということも可能です。
(3)の方式を採用している会社は、実務上は、労使協定によって計画的付与を実施しているというよりも、年度の初め等において、年休カレンダーへ従業員が記入するという形で取得希望日を聴取して、これを使用者の方で調整して各人ごとに取得日を定めるという方式が多いと思います。
この場合、仮に労使協定によるものでなかったとしても、年休カレンダー方式によって年次有給休暇日を特定するということが、従業員の時季指定権行使によるものと解することもできますので、違法とまではいえないと考えます。
対象にならない者を除いておく
また、計画的付与の時季に育児休業や産前産後の休業などに入ることがわかっている者、また、定年等あらかじめ退職することがわかっている者については、労使協定で計画的付与の対象からはずしておくことも必要だと思います。
「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー
竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2025年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。
オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法
社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。
社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。
当サイトで初めてご購入される方、会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。
会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。