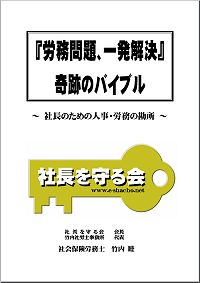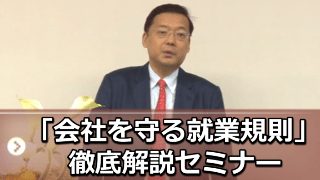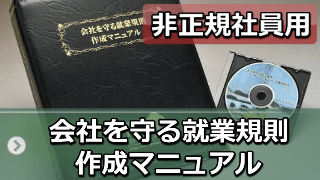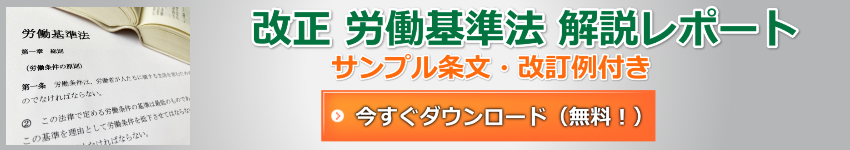パワーハラスメント
- パワーハラスメント(パワハラ)とは何ですか?
- パワハラとは、「優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」です。
パワハラとは
パワハラとは、労働施策総合推進法上の概念です。
労働施策総合推進法第30条の2第1項によると、「優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」とされています。
「優越的な関係」とは、上司・部下や先輩・後輩の関係に限られません。同僚同士や、集団・個人の関係も含まれます。(令和2年厚生労働省告示第5号)
「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは、業務上明らかに必要性のない言動や、業務の目的を大きく逸脱した言動を指します。
「労働者の就業環境が害される」とは、行為を受けた労働者が身体的、または精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることをいいます。
パワハラかどうかは、当事者の関係性や状況、背景などを踏まえて総合的に判断されます。
また、就業環境が害されているかどうかは、「平均的な労働者の感じ方」を基準に判断されます。
被行為者の主観で判断されるわけではないので、「被害者がパワハラだといったらパワハラになる」のではありません。
パワハラの6類型
業務上かつ相当な範囲で行われる注意指導は、パワハラには該当しません。
問題行動があれば、当然、きちんと注意指導をするべきです。
そのためにも、どんな言動がパワハラに該当するかを知っておきましょう。
厚生労働省は、以下の6つをパワハラの具体例に挙げています。
- 身体的な攻撃(暴行・傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
- 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
- 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
- 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
ただし、この6つは限定列挙ではありません。
これらに該当しなければパワハラではないというわけではなく、個々の事案ごと、総合的に検討されるのです。
就業規則を整備して周知する
労働施策総合推進法により、会社は、パワハラ防止に必要な措置を講じることが義務づけられています。
大企業では、2020年6月1日から義務化されました。中小企業では、2022年3月31日まで努力義務です。
措置義務に違反した場合には、厚生労働大臣は報告を求め、または助言、指導、もしくは勧告を行うことができます。
勧告にも従わなかった場合には、企業名の公表も行うことができます。
会社が講ずべきパワハラの防止措置には、以下のものが挙げられています。
- 事業主の方針の明確化、およびその周知・啓発
- 労働者からの相談に対し、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるパワハラにかかる事後の迅速かつ適切な対応等
特に1.と2.については、就業規則等に規定して、従業員に周知を図ることが、パワハラ対策の第一歩となるでしょう。
「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー
竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2025年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。
オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法
社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。
社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。
当サイトで初めてご購入される方、会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。
会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。