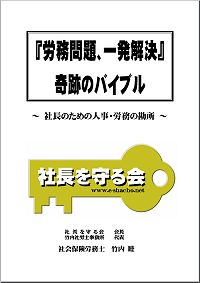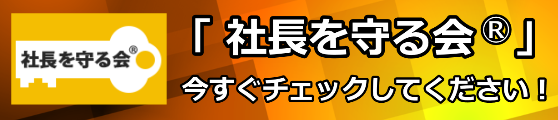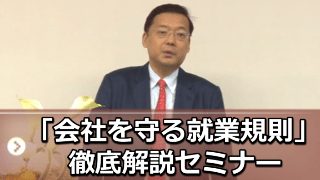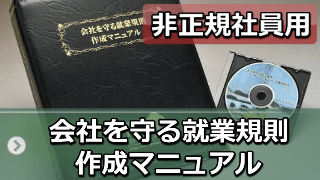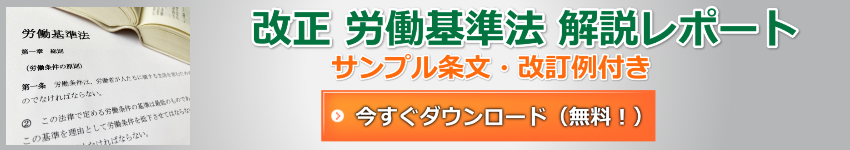有期の契約社員にも住宅手当を支払わなければならない?
- 有期雇用の契約社員に、住宅手当を支払わなければならないのですか?
- 住宅手当を支給しないことについて、不合理性を判断している裁判例を参考に、自社の待遇差を説明できるようにすることが重要です。
- パートタイム・有期雇用労働法第8条とは
- 事例詳細
パートタイム・有期雇用労働法第8条とは
- パートタイム・有期雇用労働法は、改正前は「パートタイム労働法」といわれていたもので、大企業では2020年4月1日、中小企業では2021年4月1日に施行される。
- パートタイム・有期雇用労働法第8条は、不合理な待遇差を禁止している。パートタイマーと有期雇用労働者の個々の待遇と、いわゆる正社員の個々の待遇との間において、①業務の内容、および業務に伴う責任の程度(職務の内容)、②職務の内容、および配置の変更の範囲、③その他の事情を考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
事例詳細
ある日、北大塚商事北大塚支店のA支店長と、B総務部長は、困った顔で相談していました。何に困っているのかというと、北大塚支店で数年前から働く契約社員のTさんの処遇についてです。
Tさんは、契約社員として1年間の有期雇用契約を締結し、正社員と同様に営業業務に従事してきましたが、先日、「正社員に支給されている住宅手当は、自分には支給されないのでしょうか?正社員と同じ仕事をしているのですが・・・」と聞いてきたのです。
これまでなら、「契約社員だから正社員の給与規程は適用されません」と答えればよかったのですが、Tさんは政府が進めている「同一労働同一賃金」を念頭に置いた上で質問をしてきているようなのです。
さて、A支店長とB総務部長の会話に戻ると・・・
Bさん、Tさんにも住宅手当を支給しないといけないんですかね? Tさんに支給すると他の契約社員にもという話になり、かなり人件費が増えることになりますが・・・
弊社は大企業なので、2020年4月1日から例の『同一労働同一賃金』のガイドラインに沿った対応をしないといけないし、待遇の違いについて説明を求められたら答えないといけないと、先日顧問弁護士からもアドバイスを受けました。ただ、先生によると、2020年4月1日の前でも労働契約法第20条の適用があるので、説明義務はともかく、現時点でも①業務内容と責任の程度、②職務内容と配置の変更の程度、③その他の事情に照らしあわせて不合理なものであってはいけないとされているとのことです。
うーむ、よく分からないのですが、それは具体的にはどういうことなんですか?
簡単に言えば、Tさんは有期雇用で、営業業務に従事していますが、同じ営業業務に従事している正社員と比較して、待遇に差があるのなら、先ほどの①から③の違いによるものでないといけないということなのです。この条文自体は、パートタイム・有期雇用労働法第8条に統合されますが、パートタイム・有期雇用労働法でも同内容なので、状況は変わりません。Tさんは正社員と同様に営業業務をしているとはいえるので、住宅手当を支給しないのなら業務内容以外の理由で説明をしないといけません。
なかなか大変だなあ。そもそもなぜ住宅手当の支給を開始したんでしたっけ?
数年前に、転勤を含めた人事異動をより弾力的にしようということで、住宅手当を支給しようとなったはずです。
それで実際Bさんも大阪支社からこっちに移ってきたんですもんね。Tさんには異動があるという話をしましたか?
いえ、契約社員は基本的に採用された営業所から異動しないと説明していて、労働契約書にも、転勤はしないと記載しています。
そうすると②で違いがあるので、転勤がないから住宅手当の支給がないと説明したらどうでしょうか?
そうですね、それがいいと思います。では、私から説明しておきますので、また報告しますね。
B総務部長は、Tさんには異動がないので住宅手当がない旨を説明をするようですが、はたしてうまくいくでしょうか。
自社の事情を踏まえた対応が重要です!
2020年4月1日に施行されるパートタイム・有期雇用労働法では、同法違反について勧告に従わなければ企業名公表を行うとしたほか、原則は労使の自主的な解決を求めるとしつつ個別労働関係紛争解決制度の対象とすることとしていますが、結局のところ、企業が誰にどのような基準で手当を支給するのかは民事上の問題ですので、支給している手当、賞与、退職金などの労働条件ごとに、裁判例を参考に対応を図る必要があります。
例えば住宅手当については、正社員と契約社員間の労働条件が問題になったハマキョウレックス事件では、全国転勤の可能性がある正社員のみに支給する住宅手当の合理性を認めているほか、学校法人中央学院事件では業務内容と責任の程度の違いをもとに正規職員にのみ住宅手当を支給することの不合理性を否定しています。
つまり、こうした裁判例の内容を参考に、自社の待遇差を説明することが重要なのです。
契約社員について、職務内容の見直しと同時に、就業規則も別に作成しておかないと、不要なトラブルに発展する可能性があります。
就業規則への具体的な記載方法は、以下のセミナーで詳細を解説しています。
セミナー参加者特典として、無料個別相談で疑問点をすべて解消することもできます。
「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー
竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2025年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。
オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法
社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。
社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。
当サイトで初めてご購入される方、会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。
会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。