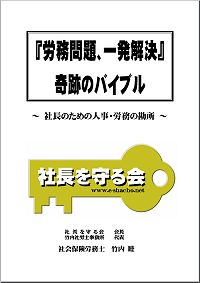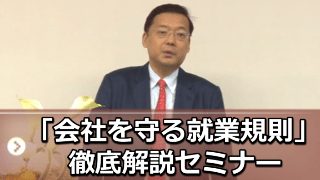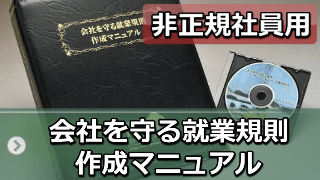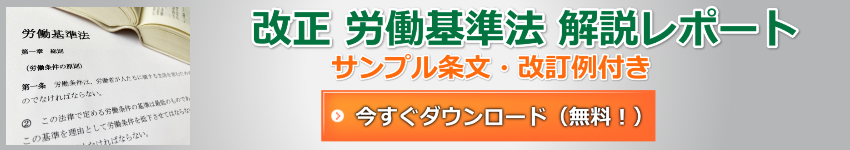労働基準法の法定休日
- 労働基準法上の「法定休日」とは何ですか?
- 法定休日とは、毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない最低限の休日です。
「法定休日」とは
労働基準法第35条は、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならないとしています。
こうした休日は、法が定めたものですから、法定休日と呼ばれ、就業規則等により会社が定める所定休日とは、区別されるものです。
また、法定休日は週1日、あるいは4週4日であるにもかかわらず、多くの会社が、法定休日を上回る休日(所定休日、あるいは法定外休日とも言います。)を設定しているのは、週40時間の法定労働時間と調整を図るためです。
週の起算日は自由に決められる
法定休日の原則は、週1日の休日です。
4週4休を採用する場合は、就業規則により4週間の起算日を明らかにする必要があります。(労働基準法施行規則第12条の2第2項)
1週間の起算が何曜日からであるかは、就業規則や労働協約等により決められます。
ただし、特段の決めがない場合は、日曜日を起点とした1週間となります。
労働基準法は、法定休日を特定することを要求していませんので、日曜日が法定休日と定められているわけではないのです。
「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー
竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2025年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。
オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法
社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。
社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。
当サイトで初めてご購入される方、会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。
会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。