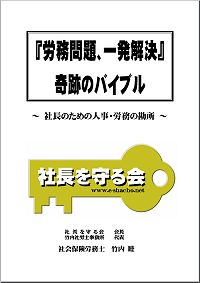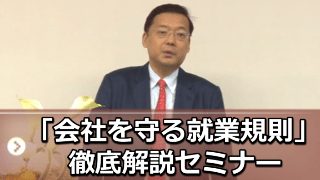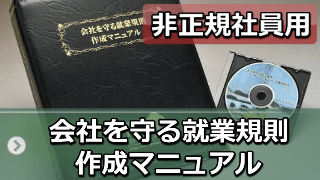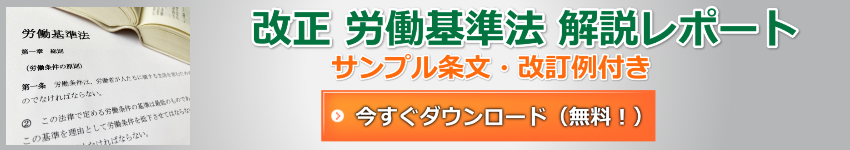年次有給休暇利用時に給与が減るのは問題?
- 年次有給休暇利用時に、手当等を減額するといった対応を取ることは問題ないのでしょうか?
- 例えば、タクシー会社の社員のような勤務形態であれば、減額することは可能ですが、これは特殊ケースといえるでしょう。
- 不利益取り扱いの原則
- 特殊ケースの裁判例
- 事例詳細
不利益取り扱いの原則
- 使用者は、・・・(略)・・・有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。(労働基準法第136条)
- 賞与査定や昇給昇格に関して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として扱うなどの不利益取り扱いは違法であるとの裁判例がある
特殊ケースの裁判例
- タクシー会社の社員について、「専ら営業収入によって利益を上げていることや、勤務表作成後の代替要員の確保が困難である」ことなどから、減給が認められた裁判例があるが、これは特殊ケースといえる
事例詳細

当社は、いわゆるタクシー事業を営む株式会社です。今年で創業40年になる当社は、約100台の車両と、約250人の従業員がいます。
当社のようなタクシー会社の経営収入の大部分は運賃ですから、乗務員の勤務成果が本人の収入に明確に反映されるよう、歩合給制度を導入しております。
そして、収益増のためには、タクシーの稼働率を高める必要がありますので、乗務員が勤務表通りに出勤した場合には、その報奨として皆勤手当も支給しています。
その他にも、安全運転手当、乗務手当、残業手当、深夜手当、公出手当等の手当を支給しています。
乗務員のAさんは、入社2年目の若手社員です。先輩乗務員のBさんは、入社5年目ですが、年齢が近いこともあって、Aさんはいろいろと相談にのってもらっています。
先輩、今月末に友達と沖縄に行こうと思ってるんですよ。4日間行ってくる予定なんですが、有給休暇を使おうと思って。使うのが初めてなんで、どうすればいいんですかね?
俺は、何年か前に風邪引いたときに、使ったきりだな。手続きは、課長に聞いてみたら?
そうですね、分かりました。明日、さっそく課長に聞いてみますよ。
でもA君さ、有給休暇を使ったら、その分水揚げがなくなるわけだから、来月の給与減っちゃうんじゃない?
マジっすか? 確かに実際に勤務した方が稼げるかも知れませんが、有給休暇なんですから、そんなに影響ないんじゃないですかねー。
翌日Aさんは、年次有給休暇取得の申し出をしに行きました。
課長、すいません。有給休暇を使いたいんですけど、どうすればよいのですか?
この届出書に必要事項を書いて、私に提出してください。Aさんは、有給休暇を使うのは初めてでしたか?
はい。先輩に聞いたら、前に1回、風邪引いたときに有給休暇を使ったことがある程度だっていってましたけど、うちの会社って、皆さん有給休暇を使わないんですか?
そんなことはないと思いますけどね。使う人は平均して月1回以上は使ってますよ。
そうなんですか。でも、有給休暇を使ったら水揚げが減るから、給与も減るんじゃないかって聞いたんですけど・・・。
そうですね。まず、有給休暇を使った日については、平均賃金に相当する有給手当を支払うことになっていますが、皆勤手当の5,000円と安全運転手当の半額の5,000円が減額となります。2回以上有給休暇を使った場合には、安全運転手当の残余分も減額になりますので、合計15,000円が減額されることになります。
えーっ! マジっすかー! そんなの初めて知りましたよ。給料減っちゃうんですかあ。
有給休暇を使った人には、共通に適用されているルールですし、就業規則にも記載されていますよ。では、届出書を提出してくださいね。
Aさんは、課長に届出書を提出した後、Bさんに相談に行きました。
先輩。やっぱり有給休暇を使うと給与減るんですね。有給休暇を使った日については、有給手当が支給されるみたいですけど、皆勤手当と安全運転手当が減るみたいです。
へ~、でも君が休めばその分水揚げが減るんだから、会社としてはしようがないのかもな。
でも、僕が休んだって、代替要員を確保できれば問題ないんじゃないかと思うんですけど。
代替要員は確保できるかも知れないけど、その代替要員は代わりに別の出番を休むことになるから、結局は1出番の休車が生じることになるだろ。まぁ有給休暇を使う月は、少ない出番でいつも以上に水揚げすればいいってことだ。
Aさんが年次有給休暇を使ったその月の支給総額は、約220,000円で、減額分の賃金総額に対する割合は約6.8%でした。
先輩、今月の給与なんですけど、やっぱり有給使ったら、いつもより少なかったですよ。
そうかー。でも、もともと水揚げによって歩合給の変動があるんだから、減額割合ってのは、あんまり関係ないんじゃないの?
そうなんですかねー。何か納得いかないですよ。これじゃ、有給休暇なんて使えないです。知り合いの弁護士に相談してみようかなあ。
さて、労働基準法第136条には、「使用者は、・・・(略)・・・有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」との規定があります。
今回のような事例では、労働基準法第136条に反しているようにも思いますが、裁判所は次のように判断しました。
タクシー会社という特性上、専ら営業収入によって利益を上げていることや、勤務表作成後の代替要員の確保が困難であり、仮に確保できたとしても、当該代替要員の乗務が予定されていた別の出番が休車になってしまうという事情から、車両の効率的な運行確保のために、乗務員の出番の完全乗務を奨励する目的で、本件減額が行われているものであり、乗務員の年休権行使を一般的に抑制しようとする趣旨・目的があるとは認められない。
そして、減額幅についても、年休権行使の抑制に結びつくほど著しい不利益を課すものではないこと、また実際に年休権の行使が、1ヶ月に11~12人に1人の割合でなされており、本件減額によって乗務員の年休権行使が一般的に強く抑制されているものとは認められないことから、年休権行使を抑制し、労働基準法が労働者の年休権を保障した趣旨を実質的に失わせるものとまでは言えず、公序に反して無効であるということはできない。
しかし、この判断がすべての企業に当てはまると解釈するのは、危険といわざるを得ません。
こうした裁判例がある一方、賞与査定や昇給昇格に関して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として扱うなどの不利益取扱いは違法であるとの裁判例もありますから、先に例示した裁判例は、今回の事例のような特殊なケースについてのみ適用されると考えておいた方が、労務管理上は無難だと思われます。
なお、年次有給休暇取得時に支払う賃金は、労働基準法第12条の平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払う賃金、健康保険法における標準報酬日額の3つの方法があります。
標準報酬日額に相当する額を支払う場合は、労使協定が必要です。
年次有給休暇取得時の賃金については、就業規則に記載しておきましょう。
年次有給休暇について正しく定めておかないと、不要なトラブルに発展する可能性があります。
就業規則への具体的な記載方法は、以下のセミナーで詳細を解説しています。
セミナー参加者特典として、無料個別相談で疑問点をすべて解消することもできます。
「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー
竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2025年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。
オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法
社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。
社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。
当サイトで初めてご購入される方、会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。
会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。