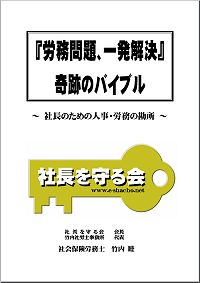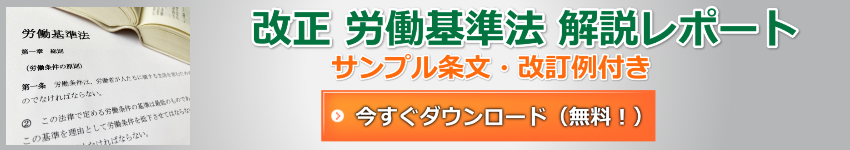精神疾患は労働災害だと主張されたら?
- 精神疾患に罹患した従業員が、残業が増えたことによる労働災害だと主張してきた場合、どのように対応するべきでしょうか?
- 基本的には労災申請の相談相手となり、申請を手伝い、労働基準監督署の調査にも協力するといった姿勢で臨むべきだと考えます。
- 労働基準監督署への対応
- 意見書を提出するとき
- 事例詳細
労働基準監督署への対応
- 会社に対する疑念を抱かせると、労働基準監督署や弁護士、組合等、外部に相談し、紛争化するリスクが高まる。
- 所轄労働基準監督署からの要請があれば、判断材料等を速やかに送付する等し、労働基準監督署の調査に協力する。
意見書を提出するとき
- 明らかに傷病の発生原因について、会社と労働者との認識が異なる場合は、所轄労働基準監督署長に対して意見を提出するという対応や、「会社は原因について判断できませんので、貴庁にてご判断をお願いします」等の趣旨を記載して、判断を委ねるといった方法も考えられる。
事例詳細
当社は、都内で広告業を営む、従業員数50名程度の中小企業です。日々の業務において、営業の業務に従事する社員については、多少の残業が発生しますが、内勤業務を行う者について、特に新人には、ほとんど残業が発生しません。
そんな中、3ヶ月ほど前に入社した事務担当のAは、仕事の覚えが悪く、作業も遅いため、先輩社員が丁寧に指導・協力することにより、なんとか所定労働時間内に業務を終えるという始末でした。
そして、困ったことに、最近では、先輩社員に手伝ってもらうことが当然かのような素振りが見受けられたため、会社としては、本人のためにもならないと判断し、Aに任せた仕事は、残業をしてでも、A自身にやってもらうことにしました。その1ヶ月後のことです。
社長、Aから連絡があり、精神疾患に罹患したとのことです。Aは、会社が残業させたことが原因だと言っています。
そうか、しかし残業といっても1日1時間くらいで、月20時間程度じゃないか。とても仕事が原因とは思えないな。当然、労災とはならんだろう。
私もそう思います。それにAの先輩社員に確認しましたが、厳しく指導したり、突き放すようなことは一切なく、引き続き優しく指導していたとのことです・・・。とはいえ、Aは、残業が原因だと主張し、労災の申請書に署名して提出してくれといっています。どのように対応したらよいでしょうか。
労災か否かは労働基準監督署長が判断する
さて、まずは、原則的な対応についてですが、労働者や労働者の家族・遺族(以下「労働者」という)が、その傷病の原因が業務にあるとして、業務災害と主張している場合は、業務災害か否かについてを当該労働者と議論すべきではなく、会社としては、労災の申請に協力して、所轄労働基準監督署からの要請があれば、判断材料等を速やかに送付する等し、所轄労働基準監督署長に業務災害かどうかの判断を仰ぐべきだと考えます。
それは、労働者と議論して、その主張を否定すればするほど、労働者としては、原因が業務にあると考えているわけですから、会社に対する疑念を抱かせることになり、労働基準監督署や弁護士、組合等、外部に相談し、紛争化するリスクが高まるためです。
したがって、会社としては、基本的には労災申請の相談相手となり、申請を手伝い、労働基準監督署の調査にも協力するといった姿勢で臨むべきだと考えます。
意見提出等をする際は労働者との関係性を考慮する
一方、今回のケースのように、長時間労働もなく、人間関係上の問題(ハラスメント)も発生していない状況下で、明らかに傷病の発生原因について、会社と労働者との認識が異なる場合は、労働基準監督署に提出する請求書の事業所証明欄に記載せず、所轄労働基準監督署長に対して意見を提出するという対応や、事業所証明欄の不動文字(印字された文言)を二重線で消し、「会社は原因について判断できませんので、貴庁にてご判断をお願いします」等の趣旨を記載して、記名押印し、所轄労働基準監督署長の判断に委ねるといった方法も考えられます。
ただし、この場合は、当該労働者としては、業務が原因であると主張しているわけですから、会社に対する当該労働者の印象は悪くなりますので、将来的な当該労働者との関係性を考慮した上で、判断されるとよいと思います。
そして、労災申請に協力すると、会社は、労働基準監督署から過重負荷や心理的負荷の有無に関連する調査を受けることとなりますので、発症前、1ヶ月ないし、6ヶ月にわたっての労働時間の確認や、不規則な勤務、拘束時間の長い勤務、出張の多い業務、深夜勤務、精神的緊張を伴う業務の負荷要因等については、会社で調査し把握しておくとよいでしょう。
能力不足や勤怠不良の社員への対応を誤ると、不要なトラブルに発展する可能性があります。
注意指導の具体的な方法は、以下のセミナーで詳細を解説しています。
セミナー参加者特典として、無料個別相談で疑問点をすべて解消することもできます。
新!失敗しない「退職・解雇」の実務セミナー
労使紛争解決を得意とする当事務所の経験とノウハウに基づき、中小企業の社長が、退職や解雇で大きな問題を抱えることなく、円満退職を実現するための方法を、リニューアルしたセミナーでわかりやすく伝授します。
2026/03/06(金)受付開始 13:00 セミナー開始 13:30~17:30 空有
オンライン動画 新!失敗しない「退職・解雇」の実務セミナーの視聴方法
社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。
社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。
当サイトで初めてご購入される方、会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。
会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。