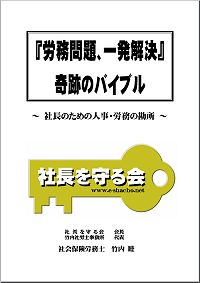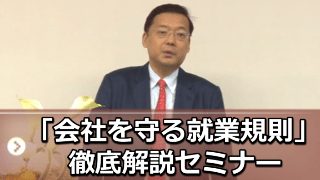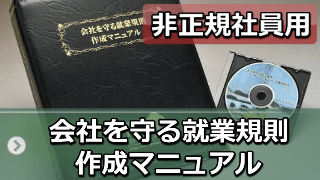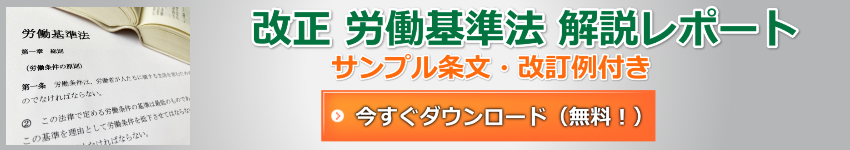会社は退職者に対して研修費を請求できる?
- 指導や訓練にかかった費用を、退職者に請求することは可能なのでしょうか?
- 事前に退職者が費用を支払うと就業規則に規定したり、契約書を交わしたりしていても、「自由意思を拘束して退職の自由を奪う性格を有する」ときは、無効と判断され、請求はできないと考えられます。
- 賠償予定の禁止の原則
- 業務との関連性
- 事例詳細
賠償予定の禁止の原則
- 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。(労働基準法第16条)
- 労働者の「自由意思を拘束して退職の自由を奪う性格を有する」と判断されれば、退職者に費用を負担させることはできない
業務との関連性
- 業務性が薄く個人の利益性が強い場合には、退職者に費用を請求できる可能性が高い
- 業務との関連性が強く、労働者個人としての利益性が弱い場合には、退職者に費用を請求できる可能性は低い
事例詳細
当社は、都内に5店舗の美容室を経営している株式会社です。当社では、特に美容技術等の指導・訓練に力を入れており、新入社員に対しても、入社当初から多額の費用をかけて指導・訓練をしています。
しかし、会社の気持ちとは裏腹に、会社の指導・訓練によって美容技術等を身につけながらも、会社の意向を無視して勝手に辞めてしまう人も、これまで何人かおりました。
そこで、そうしたことを防止するため、数年前から講習手数料契約を締結することにしました。
講習手数料契約書には、次のような文言を記載しており、当社からも十分説明し、本人もその内容を理解してもらった上で、署名・押印をもらっています。
万一、私が会社からのいろいろな指導を自分の都合でお願いしているにもかかわらず、勝手わがままな言動で会社側に迷惑をおかけした場合には、下記のことをお約束します。
記
- 指導訓練に必要な諸経費として、入社月にさかのぼり、1ヶ月につき金4万円也の講習手数料をお支払いいたします。
- 上記講習手数料は、会社より請求があった日より1週間以内にお支払いいたします。ただし、私の態度によって、会社側より講習手数料を請求されない時は、支払義務なしとさせていただきます。
A社員は、今年3月に美容専門学校を卒業し、4月から、当社巣鴨店に新入社員として入社しました。
B先輩。私が入社したときに、講習手数料契約っていう書面にサインさせられたんですけど、先輩もそうでした?
うん、私もサインしたよ。社長からも話があったと思うけど、会社の主旨も分からなくもないしね。入社して1年経てば、講習手数料は請求しないって言ってたし、それに、他の従業員が教わっていることを教えてもらえなかったら嫌じゃん。
はい。私も長く勤めたいと思っていますし、早く技術を習得できるように頑張ります。
講習は、毎週金曜日の午後7時から9時までの勤務時間外に、指導対象者を店舗内に集合させて、指導部長が洗髪、カット、カール、パーマ、セット等の指導を行う集合トレーニングと、希望者が自ら要望した時に、随時同様の指導を受ける方式によってなされていました。
A社員も、業務に熱心に取り組み、またこうした講習の成果もあって、3ヶ月の試用期間が明ける頃には、随分と技術も身についてきたようでした。
それから約2ヶ月後、仕事も順調だと思われていたA社員から、C店長に相談がありました。
やぁ、Aさん。相談って、急に改まってどうしたんだね?
・・・あのーーー、C店長。・・・実は・・・、私、会社を辞めたいんです・・・が。
えぇーーーっ! 辞めるって!! 本当に!? マジで!? ウソでしょ!? なんで!? なんかあったの!?
・・・実は、この間の講習が終わってから、みんなで食事に行ったんです。その帰り道で、お酒も入っていたんでしょうが、指導部長から交際を迫られまして・・・。
えぇーーーっ! そうだったんですかぁーーー!!! ひどい部長だな、でも、考え直す気はないのかい?
・・・はい。私もすごく悩んだんですが、・・・もうこの会社にはいられません・・・。
んー、わかりました。そういう事情なら仕方ない。でも、講習手数料を請求されなければいいんだけどな・・・。
そうですね。でも貯金もありませんから、請求されても払えません。そもそも、講習手数料契約ってありなんでしょうか?
業務性があるか否かがポイント

労働基準法第16条では、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと規定されています(金額を予定することは禁止されますが、実際の損害額を請求するのは問題ありません)。
これは、労働者が一定期間を経ずに退職しようとする場合に、違約金や損害賠償を支払わせることで、会社が労働者の足止めを図るという弊害を禁止することを目的とした規定です。
先に挙げた事例では、結局、会社がA社員を訴えて裁判になってしまいました。裁判所は、以下のように判示しました。
本件契約の目的、内容、従業員に及ぼす効果、指導の実態、労働契約との関係等の事実関係に照らすと、会社が主張するように、いわゆる一人前の美容師を養成するために多くの時間や費用を要するとしても、本件契約における従業員に対する指導の実態は、いわゆる一般の新入社員教育とさして変わらず、右のような負担は、会社として当然なすべき性質のものであるから、労働契約と離れて本件のような契約をなす合理性は認め難く、しかも、本件契約が講習手数料の支払義務を従業員に課することにより、その自由意思を拘束して退職の自由を奪う性格を有することが明らかであるから、結局本件契約は、労働基準法第16条に違反する無効なものであるという他はない。
また、類似した形態として、会社が費用を出して従業員に技能修得や海外留学をさせている場合もあると思います。
この場合においても、修得(留学)後ただちに辞められては困るので、その足止めのために、費用を会社が従業員に貸与する形式をとり、修得(留学)後一定期間勤続の場合は、その返還を免除するという契約を締結したり、就業規則に規定したりしていることがあります。
そこで、このような契約が労働基準法第16条に規定する「賠償予定の禁止」に違反しないかが問題となりますが、裁判所は、次のように判断する傾向にあります。
まず、修得(留学)等の経緯・内容に照らし、業務性が薄く個人の利益性が強い場合には、本来労働者が負担すべき費用を労働契約とは別個の消費貸借契約(返還債務免除特約付)で会社が貸し付けたものであって、労働契約の不履行について違約金・賠償予定の定めにはあたらない。
逆に、当該企業の業務との関連性が強く、労働者個人としての利益性が弱い場合には、本来会社が負担すべき費用を、一定期間以内に退職しようとする労働者に支払わせるものであるから、就労継続を強制する違約金・賠償予定の定めにあたる。
もちろん、事案によっても異なりますが、まずは修得(留学)等に関して、「業務性」の有無に着目してみることが重要なポイントといえるでしょう。
教育訓練について正しく規定しておかないと、不要なトラブルに発展する可能性があります。
就業規則への具体的な記載方法は、以下のセミナーで詳細を解説しています。
セミナー参加者特典として、無料個別相談で疑問点をすべて解消することもできます。
「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー
竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2025年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。
オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法
社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。
社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。
当サイトで初めてご購入される方、会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。
会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。